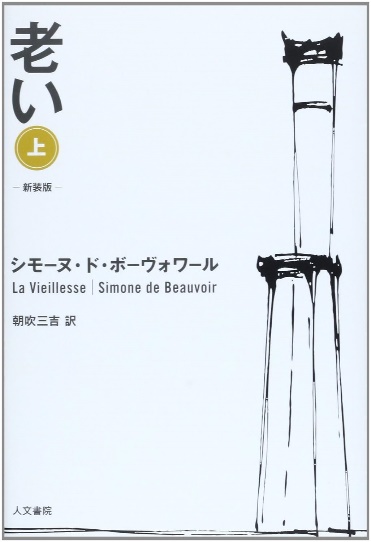34歳の時に長女を、37歳で次女を授かり、熊大からUCLA、水俣市総合医療センターと夫の勤め先が変わる度に専業主婦としてついて行った。水俣時代には次女が産まれた。水俣市洗切町の病院の官舎に住んだ。水俣病で世界的に有名になった地だが、海は美しく、私は二児の母としてママさんバレーボール大会やママさんコーラスを楽しんだ。魚が新鮮でおいしく水公舎という地元のスーパーで鯵を買い、腸を取って一尾丸ごと揚げて野菜の餡を掛ける料理などを楽しんだ。専業主婦だったので、苦手な掃除にも力を入れ、古い官舎を綺麗にした。長女は庭の木登りが上手なさほちゃんと呼ぶ地元の女の子と幼稚園から帰ったあと官舎で遊び、布団に寝せている次女を踏み潰す勢いで駆け回るので、ハラハラした。
平凡で幸せな日常。ただ私はあまり名を呼ばれない。○○先生の奥さん、○○ちゃんのお母さんとだけ呼ばれる。私の中で焦燥感が募った。こんな日常で良いのだろうか。私は有意義なことをしているのだろうか。子どもたちは可愛く激務にある夫の役に立つのはうれしかったが、「私」はいったいどこに行ったのだろうか。その思いを抱えながら、バギーを押して図書館に通った。ここでも様々な本を読み、少しでも自分自身を磨きたいと思った。ロサンジェルスで住んでいたバデュー通りの傍にも図書館があり、そこには日本語の本のコーナーもあって借りて読んでいた。本はいつも友達だった。水俣で名前を呼ばれない私も、本には一人の興梠順子として対峙できる。
レポーターとしてある程度評価された経験が、奥さんとかお母さんとだけ呼ばれるのをある種の屈辱と感じてしまう気持ちを生むのか。くだらないプライドのせいか。報道部にいた頃はあんなに辞めたいと思っていたのに。私は再びボーヴオワールの「第二の性」の理論に立ち戻り、自分を省みていた。ボーヴォワールは、「人は女に生まれるのではない、女になるのだ」と言った。私は「女」つまり夫の妻、子供たちのお母さんにだけなっているに過ぎない日常を生きているのでは?家族に合わせ、家族を第一にする日常生活の中で、興梠順子という自己はいったいどこにいるのだろう。自己実現とはどんなものなのだろう。一度は社会的に一人の人間として扱われた自分を経験した私は、もう一度その自分を実践したいという気持ちとこれではダメだという自分への失望感の中にいた。
紹介する本:『老い』シモーヌ・ド・ボーヴォワール
ボーヴォワールのこの著作は彼女が62歳の時に書いたものです。『第二の性』と並ぶ名著としてNHKの「100分de名著」にも取り上げられました。
「第二の性」では、女は女であるが故に人間性を疎外された存在であると論じたボーヴォワール。「老い」のなかでも老人が老い故に人間性から疎外された存在だと指摘しています。女も老人も社会から「疎外された存在」というのです。
ボーヴォワールは、「老齢は我々を不意にとらえる」と書きます。老いとは他者から指摘されて知る、認めがたいものなのです。この「老い」から目をそらさずに、外部(生物学的、歴史的、社会的見地)からと、内部(老いの発見と受容)からの両面で、徹底的に「老い」を論じていきます。
ボーヴォワールがこの著を書いた年よりも10歳も高齢の私です。自らの年を実感することも多く、他者から指摘されることもあります。老いの受容と次の人に託すこと。これは絶対に必要なことであり、私も近い将来、引退しなければと考えます。私は祖父や父と違って平凡な人間です。壺溪塾を次世代に「繋ぐ者」に過ぎないのです。あまり遅くならないうちに、と考えています。