
匂いが記憶を呼び覚ますことがある。これをプルースト効果と呼ぶそうだ。プルースト効果は、特定の匂いを嗅いだときに過去の記憶や感情が無意識的に呼び覚まされる現象を言う。それは、フランスの作家マルセル・プルーストの長編小説『失われた時を求めて』に由来している。作中で紅茶に浸したマドレーヌを口にした瞬間、その香りに刺激されて幼い頃の風景が鮮やかに蘇る場面があるのだ。
読者もプルースト効果の記憶をお持ちなのではなかろうか。
私はキャベツをよく千切りにする。トンカツの付け合わせにするし、キャベツの千切りに塩を掛けてしばらく置き、出て来る水をぎゅっと絞ってドレッシングとマヨネーズ、ヨーグルトと和え、コールスローサラダを作る。このキャベツの千切りをするときにいつも思い出すのが、幼い頃、坪井の実家の庭で飼っていたニワトリにおばあちゃんとハコベや大根葉と一緒にキャベツを刻んで餌をやっていた記憶である。私の中で緑のキャベツはニワトリの赤いトサカの記憶と結びついている。「わたしを語る」に寄せられた読者からのお頼りのうち71歳の卒業生の方から、「坐禅を組んでいたことを畳の匂いとともに思い出しました」というお便りをいただいた。百畳以上もある畳敷きの旧教室で、木庭家の四人姉妹は、机が後ろの方に寄せられた夏休みなどにボールを追いかけたりして走り回って遊んでいた。そのときも畳の匂いがしていた。

良い香りが好きだ。クチナシを始めとして、バラの花、ツバキの花、梅の花、百合の花、それぞれの季節ごとの花は見るのに美しいだけでなくとても良い香りを届けてくれるので、室内にはいつも花がある。
部屋にアロマオイルを置くのも好きだ。リラックスできるし、癒される。
香水も好きで、お気に入りはエルメスのカレーシュ。しかし、仕事場の壺溪塾につけていくのは最低限に抑えている。なぜならば、香水臭いから面談したくないと一度塾生に言われたからだ。確かに他者のつけている香水が強すぎるのは私も苦手だ。
味覚や視覚などの五感の中で香りは直接脳に働きかけるものと言われている。香りが脳に到達するまでわずか0.2秒だという。これは、香りは言語などを司る大脳新皮質を経由せず、本能的な行動や直感などを司る大脳辺縁系に直接届くからだ。大脳辺縁系の一部には記憶を司る海馬という部位がある。それが、香りが記憶と結びつく理由の一つだ。海馬の研究で知られる池谷裕二氏の『進化しすぎた脳』には、受験生が聞いて有用なエピソードが詰まっている。その本の中で池谷氏は「意識とは何か」と問いかけている。意識とは「判断できること」「行動を選択すること」という。その意味でハブや蛙には意識がない。ハブは人間に噛みつくが人間と判断して噛みつくのではない。熱に反応するのだという。だから赤外線を当てても噛みつく。また蛙に至っては目の前に飛んで来るものがあれば全てに噛みつく。同じ文脈で私たちが香りを好き、と思うのは意識ではない。無意識の領域のものだ。私たちが癒されるためには、無意識の領域に働きかけることが大事だと分かる。
匂いに関しては良いものばかりではない。またSNS上の炎上を呼ぶケースもある。ある女性フリーアナウンサーが「男性の体臭」を巡る発言を行い、大炎上したという。「ご事情があるなら本当にごめんなさいなんだけど、夏場の男性の匂いや不摂生している方特有の体臭が苦手すぎる」とXに投稿し、シャワーや制汗剤の使用を呼びかけるものだったが、その言い回しに批判が相次いだそうだ。
この体臭や強い香水などで周囲に不快感を与えるスメハラ(スメルハラスメント)が社会問題化しつつあるという。これも匂いが脳にダイレクトに届き、快不快が瞬時に意識される故であろう。
紹介する本 「進化した脳」 池谷裕二
池谷裕二氏の『進化しすぎた脳』は受験生にも有用な脳の働きについて海馬の研究者としての豊富な知識を元に素人にも分かりやすい筆致で書いてあるとても面白い本です。以下に本の中で「面白い」と感じ、静坐で塾生に伝えた内容を紹介します。
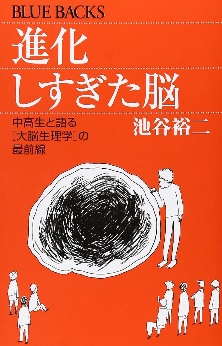

「意識」とは何か
「意識」とは何だろう。この問いは哲学者ではないにしても、自己を認識し始めた頃、一度は自らに問うた人が多いに違いない。池谷氏はこの問いに答えるのに、昆虫を持ち出している。たとえば毒蛇のハブは、動物―特に哺乳類が近づいて来ると噛みつく性質を持つ。どうして噛みつくかというと威嚇したり身を守ったりするためだが、そのメカニズムを調べると至極単純だ。温かいものを感じると(たとえそれが赤外線でも)がぶっと噛みつく。蚊は温度や二酸化炭素に反応して刺す。かえるは目の前を飛んでいるものがあると、食べ物ではなくてもぱくっと噛みつく。
こういうハブとか蚊とか蛙の行動は意識だろうか。いや、意識ではない。彼らは目の前のものを餌だと判断しているわけではなく、一種の反射で行動している。それは、極言してしまうと自動販売機のようなマシーンと同じで、入れてボタンを押せばジュースがポンと出てくるようなものだ。その限りにおいては完璧だが、それ以外の表現ができない。つまり意識の定義の一番目は「判断できること」である。これをもっと科学的な言葉で表すと「表現を選択できる」ということだ。自分が歩こうとしてもいいし、立ち止まろうとしてもいい。それは自分が行動の表現を選択していることだ。呼吸をしよう、呼吸を止めよう、そうやって表現を選択できることが「意識」なのだ。
「クオリア」について
では、「感情」とは「意識」だろうか。好きだとか楽しいなどという感情は、自分ではコントロール不能なものだ。つまり表現を選択できないので、「意識」ではなく、「無意識」というべきだ。音楽を聴いて、すごく美しいと思ったり、悲しい気分になったり、リンゴを食べておいしいとか甘酸っぱいとか感じる、そういう生々しい感覚のことを「クオリア」という。日本語に訳すと「覚醒感覚」となる。「クオリア」はラテン語で「質」という意味で、英語の「クオリティ」(quality)の語源だ。この「クオリア」は表現を選択できない。「脳」が美しい、悲しいなどと解釈して「私」にそう教えているから、そう感じるのはしょうがない。「感情」は意識的に変えられないのだ。このように「意識」と「無意識」の違いについて考えていくと、受験生の勉強の方法について極めて示唆的な事実に気づく。理性でどんなに勉強しようと思っても、身体がいうことをきかないと感じる時がある人はいないだろうか。勉強するということは、勉強という行動を自ら選択するのであるから、意識の領域に属することなのだが、嫌々ながら机に座ってもちっとも頭に入ってこないという経験をした人は多いだろう。
勉強の際の「クオリア」
ここで「クオリア」という概念を思い出して欲しい。たとえばモーツアルトの音楽を聴いたときに「おお、すごいな、美しいな」という感覚を持つ。これを「クオリア」という。この「クオリア」を勉強の領域に何とかもって来られたら、どんな人でも、自ら進んでどんどん勉強していくのではないか。得意な教科には多かれ少なかれこの「クオリア」を感じる瞬間があるものだ。私は受験生の時から、国語がとても好きで得意だった。試験中に評論文を読んでいて、著者の考察に感動し、問題を解くよりもその考えを発展させることに一生懸命になる場面があったのだが、一見回り道に見えて、そのような思考を重ねることが、問題を解く技術力を自然にアップさせることに繋がった気がする。数学を解いていて、自力で解ききった時、この「クオリア」を感じるという人もいるだろう。たとえばエンドレス数学で、最初は難問と感じて解けなかった人も、粘りに粘って時間が掛かっても最後に解けた瞬間というのは「クオリア!」に違いない。ところが解らないからと言って解答を見る。それでは「クオリア」は得られない。実感の中の「クオリア」を得るには、あくまで自分で解くしかないのだ。
勉強に行き詰った時、「クオリア」を感じるように仕向ける勉強法を試してみよう。つまり苦手科目を普通の科目にするのも大事だが、得意科目をより得意にするのだって良い方法だ。受験という枠組みは捨てて、知的好奇心の赴くままに学問を探求していくというタイプの塾生がいる。時間が掛かるのはお構いなしに一つのことを粘っこく探求していく。この探求型タイプの人たちは受験にも成功する確率が高い。ただ、勉強における「クオリア」は、最初苦しくても努力を積み重ねることのあとにやってくる場合が多い。砂の上に城は築けないように基礎基本をマスターしてこそ、勉強における「クオリア」が体験できるのだ。そこで、やはりつまらなくても基礎基本の習得は欠かせない勉強法となる。ただそのことを毎日の規則正しい流れに添って習慣にできるというのは壺溪塾に通っている強みだ。基本テスト、壺溪塾.comなど様々な基礎基本をインプットする手段を大事にしながら、一つひとつを積み上げていって欲しい。
私たちの脳の働きをよく知った上で、その特長をおおいに利用し、我慢強くなおかつ楽しく勉強する時、君たちの勉強に対する姿勢そのものが磨かれるに違いない。
